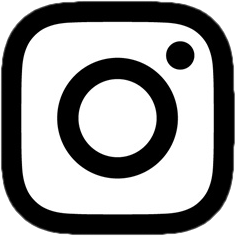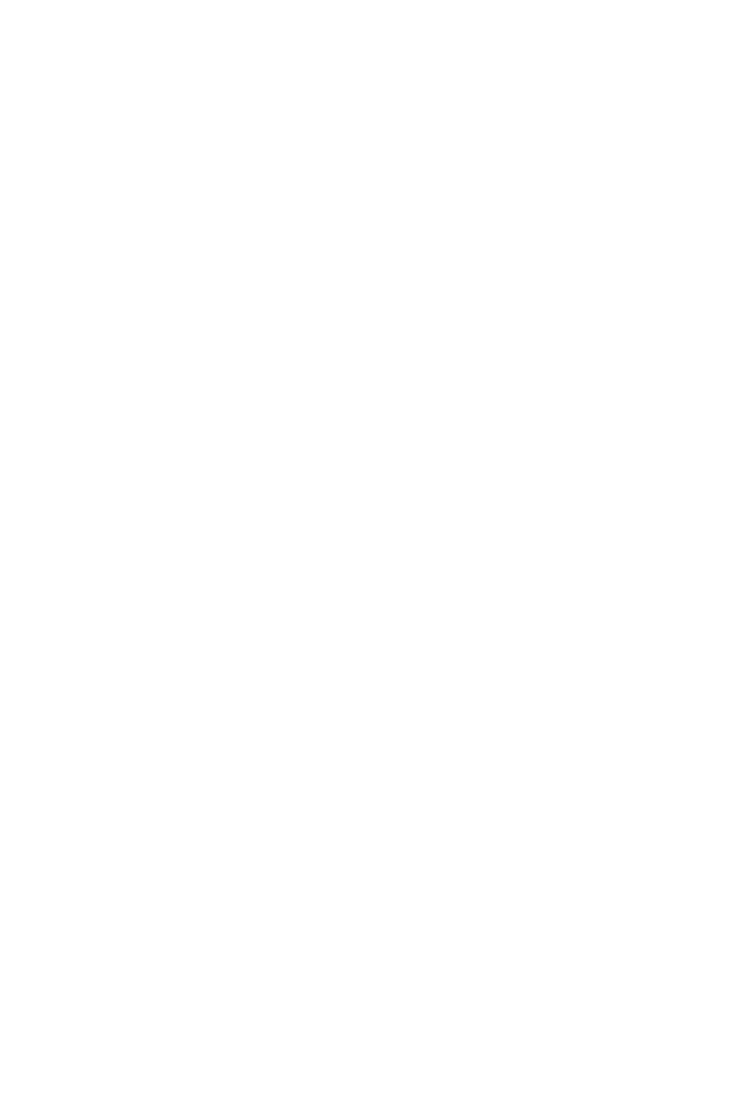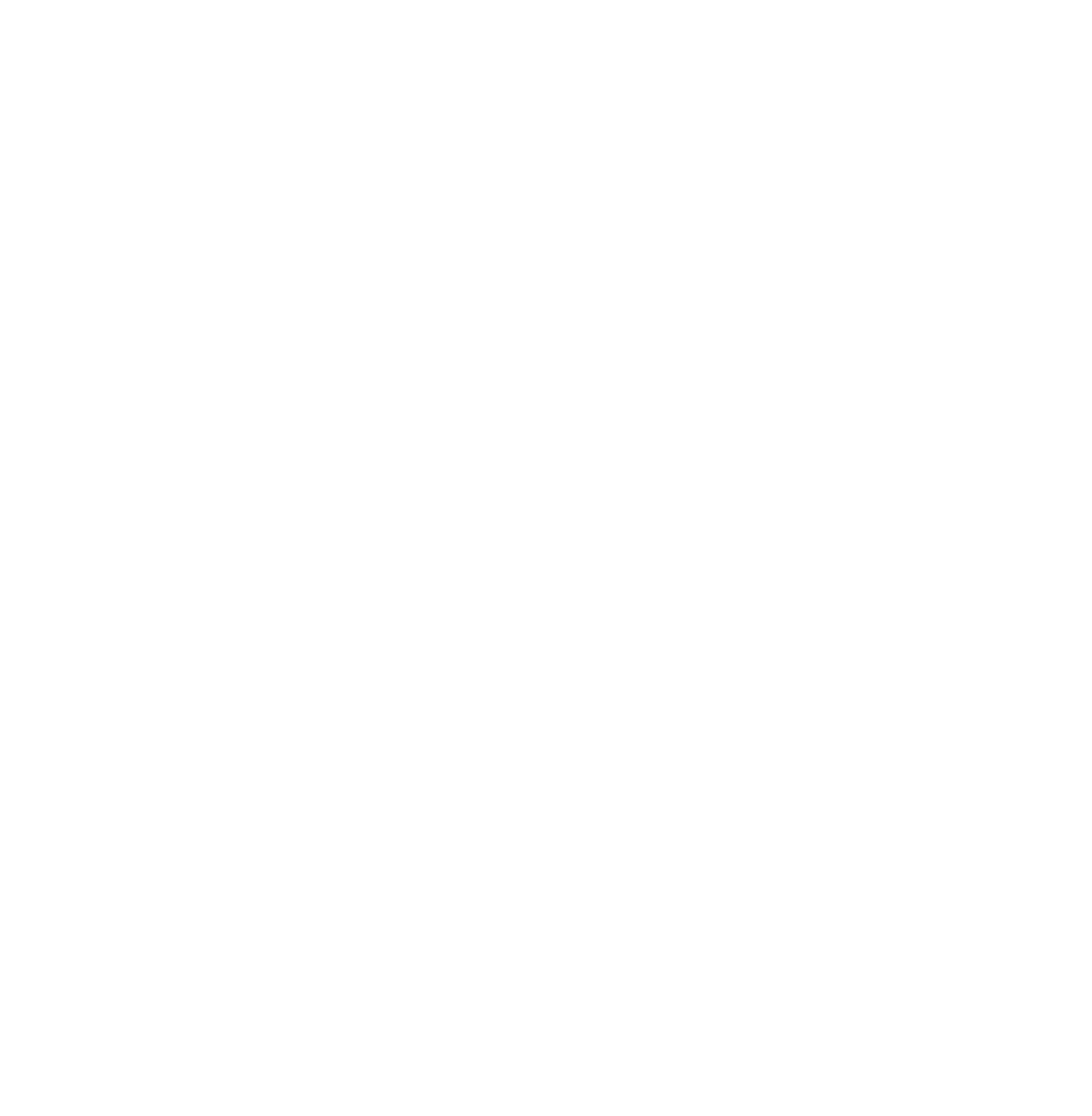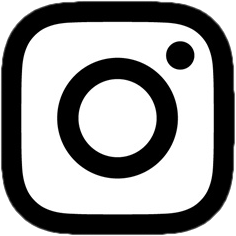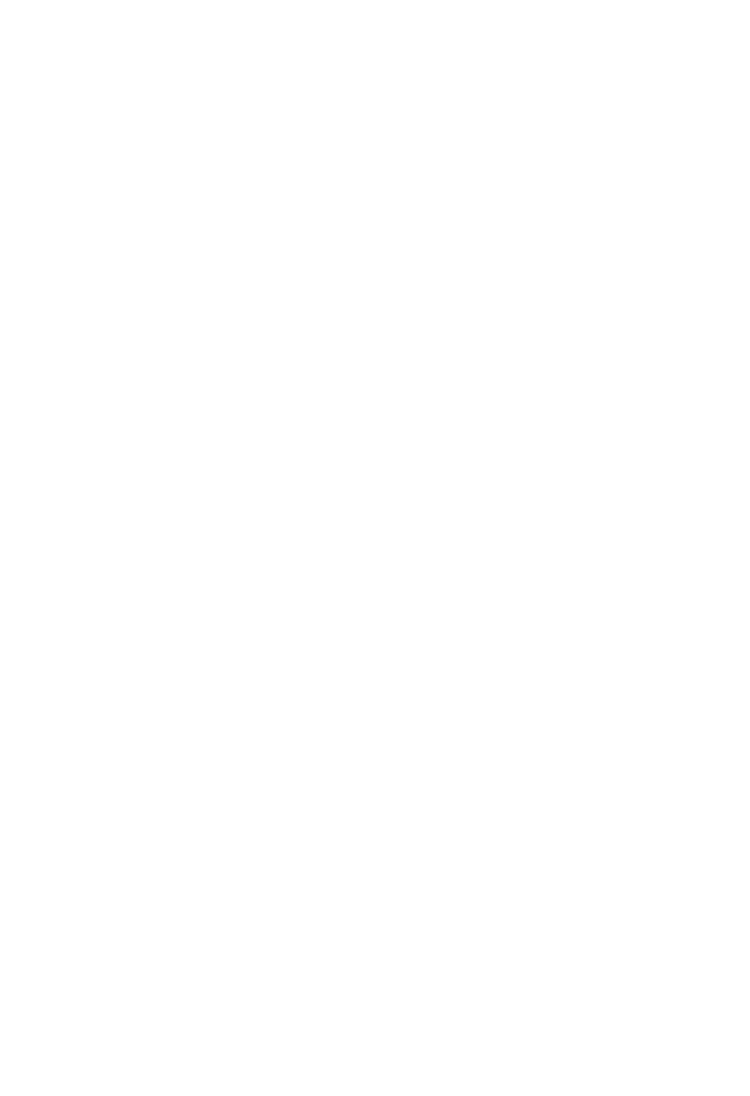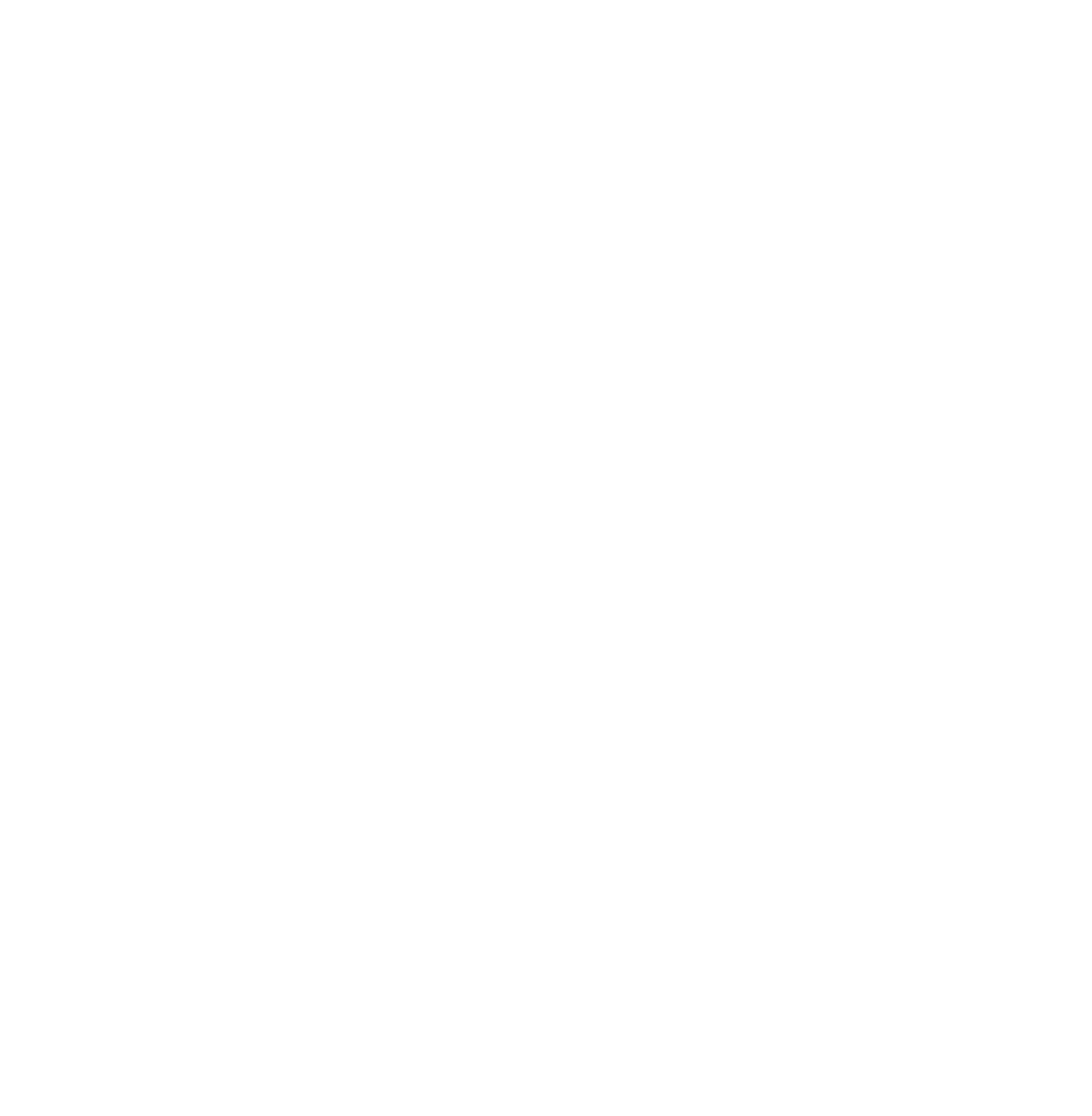Review
佐藤ひでこ紹介文
2020年の2月のこと、筆者は、思いがけずして非常に幸福な体験に遭遇することになった。それは、佐藤ひでこ氏の演奏との出会いである。彼女は、東京音大を卒業後、ダン・タイ・ソンの直弟子となって各国で多くレッスンを受けた他、ポーランドのショパン・アカデミーやクラコフ音楽院でも学んだピアニストである。それ以後は、ヨーロッパ各地で研鑽を積みながらかなり華やかな活動を行っていた模様であるが、1995年に帰国した直後にフォーカル・ジストニアを患い、約21年間試行錯誤し続けた結果、彼女独自の鍵盤リハビリのみで2016年に完治したという数奇な運命をたどった人物である。そして、思いがけない運命に苦しめられた彼女は、シャープな感性と純粋無垢で真摯な音楽性の持ち主であり、そのナイーヴな心で各作品に秘められたロマンや作曲家の心情を豊かに感じ取り、それを物おじしないで大胆に前面に押し出すことによって、とても純度が高くセンシティヴな表現を聴かせていた。彼女独特の透明度が高く磨き上げられた音楽は、感情表現の豊かさに於いてもみるべきものがあったが、そうした演奏を聴きながら筆者の心に浮かんできたのは、「あるいは神は、彼女の魂と音楽を一層清め、さらに純粋なものへと磨き上げるために、難病というかたちで厳しい試練を与えたのではないだろうか」といったとりとめのない空想であった。彼女の音楽は、それ自体としては極めて自然でクセのないものであり、透明度の高さや特有の清らかさを随所で強く印象づけていたが、音楽をこうした捉え方ができることは、別の角度から考えると非凡な個性以外の何物でもなくこのピアニストが非常に貴重な才能を有している事実を実感させた。ここまで以前に執筆した批評文を流用しながら彼女の独自性について語ってきたが、今回こうして彼女のデビュー盤がリリースされるのは、筆者としても大変嬉しいことである。ここに聴く彼女の演奏は、以前のリサイタルの時と本質的には違いがないが、さらにその持ち味が磨かれていることが好ましく、そこでは、作曲家の魂と彼女の魂との邂逅が実現されている様相をも随所で感じ取ることができたのである。
柴田龍一
(フォンテックCD FOCD9889ライナーノートから転載)
ぶらあぼ 2020年2月号 (Pick Up) より
佐藤ひでこピアノリサイタル
苦難を超えて突き詰める、美しい音色の世界
佐藤ひでこは東京音楽大学経てポーランドに渡り、同地を拠点にロシア、カナダなど世界を巡って研鑽を積んだピアニスト。名教師であるロシア・ピアニズムの伝道者であるゲンリフ・ネイガウス20世紀を代表するピアニストのエミール・ギレリスの孫弟子としてロシア・ピアニズムを会得し、自らの研究した奏法を結び付けて独自の奏法を編み出している。帰国直後の1995年にはフォーカル・ジストニアに罹患。21年に及ぶ懸命なリハビリを経て、見事に完治。2018年のリサイタルは大盛況となった。美しい音色が高く評価されている佐藤が今回演奏するのは彼女の”核”ともいえるショパンのピアノ・ソナタ第2番をはじめ、シューマンの「蝶々」とブラームスの「三つの間奏曲」。いずれの高い技術と歌心、そして研ぎ澄まされた高い音色が求められる。常に奏法を研究し、音色に対する強いこだわりをもつ彼女だからこそ展開できる音世界をぜひ味わってほしい。
文:長井進之介
ショパン 2020年 4月号より
2月27日 / 東京文化会館小ホール 佐藤ひでこピアノリサイタル
佐藤ひでこ
「スコアの彼方から聴こえてくるファンタジー」
奏者は、ロシアンピアニズム教祖ゲンリヒ・ネイガウスの弟子やダン・タイ・ソンに師事し、ワル シャワ他ヨーロッパ各地、カナダで研鑽を積むが、帰国直後フォーカル・ジストニア発症。21年におよぶ闘病の末2016年に完治、演奏活動再開。冒頭のブラームス《3つのインテルメッツォ》第1曲を耳にした瞬間、その優しさと暖かさに満ちた響きに引き込まれる。 遠い過去に万感な思いを馳せ、全てを許し、また受け入れるかのよう……。第2曲も、旋律とバスとの調和が美しく、音楽の真実にあふれる。第3曲は、波立つ心に、かすかな希望と祈りが訪れるよう……。次に、シューマン《パピヨン》。何と自由に美しく飛翔する音楽だろう!ポエジーと香り立つロマンティシズムが聴くものにファンタジーを贈り届ける。後半はショパンのピアノ・ソナタ第2番《葬送》。デモーニッシュなスタートからすでにただならぬ表現力を感じる。決してアグレッシブにならず、絶えず優しさと気品が漂う一方、劇的な表現力を有し、音楽そのもののスケールが大きい。2楽章も緊迫感から一転ノスタルジックな中間部が美しい。3楽章の葬送行進曲は悲しみを深く個人的にとらえ、荘重な中、突き抜けるような透明な音楽が流れる。中間部の歌も限りなくピュアで優しい。フィナーレは幽玄で厳粛。最後の一音を敢えてPPで表したところに奏者の深い意図を感じた。
(藤巻暢子)
音楽現代 2020年5月号より
演奏会評 ピアノ・鍵盤楽器から
佐藤ひでこ ピアノ・リサイタル
この日も振袖で履物なし。上体が固定されて無駄な動きなく、案外弾きやすいのでは。ただ聴き手にとって着物姿は重要でない。ブラームス / 3つの間奏曲作品117は自分を消していくように黙考から入っていった。寂寥感で覆われる。ドイツ・ロマンが幽玄と結びついた淑やかな歌い。ゆったりとした腕の上下動が手首を軸に指の圧を微調整する、ロシア奏法。しかも求める音がそうさせている。シューマン
/ パピヨンも詩を朗読するような抑揚がつく。どのモチーフも閃きに溢れ、着想がはじける。ショパン / ソナタ2番の大きな跳躍に難はなかった。1楽章、独特のシンコペーションを刻みながら長大なフレージング、やはりロシア流。〈葬送〉の悲しみはありえないほどの心底に沈み、プレスと楽章はまさに再創造。時間が圧縮され、リレーフのような造形を浮かび上がらせる。身を投じるあまりもったいない場面もあったが、場数の問題だ。比類ないピアニストでありアーティストを今後もフォローしていく。
(2月27日、東京文化会館小ホール)
(高塚昌彦)
ムジカノーヴァ 2020年 5月号より
演奏会批評 関東の演奏会から
佐藤ひでこ
佐藤ひでこは、東京音大を卒業後、ダン・タイ・ソンの弟子となって各国でレッスンを受けた他、ポーランドのショパン音楽院やクラコフ音楽院も修了したピアニストである。それ以後の彼女は、ヨーロッパ各地で研鑽を積みながら演奏活動を行っていた模様であるが、1995に帰国した直後にフォーカル・ジストニアを患い、約21年間試行錯誤し続けた結果、独自の鍵盤リハビリのみで2016年に完治したという数奇な運命をたどった人物である。そして 、当夜の彼女のリサイタルでは、ブラームスの《3つの間奏曲》、シューマンの《パピヨン》ショパンの《ピアノ・ソナタ第2番「葬送」》が演奏された。佐藤は思いがけない運命に苦しめられた一方、非常にシャープな感性と純粋で真摯な音楽性の持ち主であり、そのナイーブな心でそれぞれの作品に秘められたロマンを豊かに感じ取り、それを物おじしないで大胆に前面に押し出すことによってとても純度が高くセンシティブな表現を聴かせていた。彼女独特の透明度が高く磨き上げられた音楽は、感情表現の豊かさにおいてもみるべきものがあったが、そうした演奏を聴きながら筆者が感じたことは、「あるいは神は彼女の魂と音楽をさらに純粋なものに磨き上げるために、病気というかたちで厳しい試練を与えたのではないだろうか」といったとりとめのない空想であった。彼女の音楽は、それ自としては極めて自然でクセのないものであり、透明度の高さや特有の清らかさを随所で強く印象づけていたが、音楽をこうした捉え方ができることは、別の角度から考えると非凡な個性以外の何物でもなく、このピアニストが非常に貴重な才能を有してる事実を実感させた。今後の活躍が楽しみであり、大輪の花を咲かせてくれることを祈りたい。
(2月27日、東京文化会館小ホール)
柴田龍一
ぶらあぼ 2018年5月号 (5月の注目公演) より
佐藤ひでこ(ピアノ)
5/30(水)19:00浜離宮朝日ホール
東京音大からポーランドやカナダに学び、国際派ピアニストとして将来を嘱望されていた矢先、難病に侵され やむなく活動を停止した佐藤ひでこしかし、2年前に奇跡的に回復を果たし、今年3月には「23年ぶり」のリサイタルを成功させた。今回はベートーヴェンの31番、シューベルト第13番、プロコフィエフの第6
番と3つの名ソナタを軸に。蘇ったロシアン・ピアニズムで紡ぐ美音に、奏でる喜びを託す。
(文・笹田和人)
ショパン 2018年 8月号より
佐藤ひでこピアノリサイタル 5月30日 / 浜離宮朝日ホール
「23年ぶりのリサイタル、生命力に満ちた情緒豊かな表現」
欧州やロシアなどで学び、研鑽を積んだ佐藤ひでこは帰国後のデビュー公演後にフォーカル・ジストニアに罹り思うように動かせなくなって20年以上も弾くことができなかった。それが一昨年に完治を遂げた。この復活リサイタルではドビュッシーと三曲のソナタを選曲、まったくブランクを感じさせない優れたテクニ
ックを駆使して、作曲家と作品への深い理解を思わせる真摯で様式感のある表現で聞かせた。ドビュッシーの二曲〈パックの踊り〉での軽やかさ、気まぐれの味も出しつつ、なめらかに飛びまわり、リズミカルに踊るよう、〈ミンストレル〉では神経質な空気を作りつつ、機知に富む表現で奏された。三曲のソナタ、プロコフィエフの《ソナタ第6番》をエネルギッシュに、独特の叙情性も充分表し、とりわけ第1楽章はダイナミックにやがて深みへと入り込み、終楽章では高音の際立つ疾走、第1副主題も印象的に、勢いのある弾奏で聞かせた。一方シューベルトの《ソナタ第13番》D664では自然な表現で、旋律の素朴な味を引き出し、ときに心を透くような清澄さ、とりわけ第3楽章は流麗で、リズムの魅力も感じられた。最後はベートーヴェンの《ソナタ第311番》作品110、第1楽章でのしみじみとした味わい、情緒豊かに移りゆき、第2楽章は程良く強弱がつけられ、中間部が足早かつ軽やかに表された。終楽章は内なる声のよう、切々と紡がれ、フーガでは遭進するような奏楽、その頂点は確信的で生命力に満ちあふれる弾奏となった。
(菅野泰彦)
音楽現代 2018年 8月号より
佐藤ひでこ ピアノ・リサイタル
手の病のため演奏を休止、克服して開いたリサイタルは23年ぶりのとのこと。だがブランクは感じさせない。なんと着物で登場。そのユニークさは演奏にも表れる。ドビュッシー/パックの踊り、ミンストレル。音楽は凸凹豊か、抜群のリズム感で弾ませる。なのに潤いある音質。入り出のフレージングの妙、間どりも巧み。これらと繋がりよくプロコフィエフ/ソナタ6番。「戦争ソナタ
」と床の付く振袖、締め付ける帯は不思議な光景体の動きは制約され、キュービック気味になるけど、なぜかプロコフィエフに適合。打鍵はキッチリガッチリでも脱力して・・・その瞬間、どこかの>に全体重をのせ、完全に立ち上がった。でも決して乱暴ではなく、求める音に完全に奉仕。後半にシューベルト/D664、ベートーヴェン/ソナタ31番。技術を切り替え、和風の淑やかさへ移行させたが、やはりプロコのffが残って集中を削がれたよう。1日で2つの離れた高峰は避けるべき。とはいえ、見る価値もあるリサイタルは初めてだ。
(5月30日、浜離宮朝日ホール)
(高塚昌彦)
ムジカノーヴァ 2018年 9月号より
演奏会批評 関東の演奏会から
佐藤ひでこ
長く患っていたフォーカル・ジストニアが完治しての復帰リサイタルだという。しかし当夜の演奏にはジストニアの影響は微塵も感じられなかった。人知れぬ苦労があったとは思うが、見事である。佐藤は良い意味で楽曲によってスタイルが変わるピアニスト。前半と後半では別の魅力があった。前半のプロコフィエフ《ピアノ・ソナタ第6番》では、敢えて作品と自己の距離を取り、差し迫った焦燥感を前面に出すのではなく精緻な楽曲の構造をよく理解して、第4楽章で集中度が最大になるように全体を統一的にまとめあげていた。メカニックが安定していたからこそ、第4楽章が躍動感に満ちた演奏になったのだろう。後半では、まずシューベルト《ピアノ・ソナタ第13番》D664が演奏された。イ長調のソナタの魅力を、佐藤は心からの歌で優しく表現していた。第2楽章のパストラルは印象に残った。素晴らしかった。第3楽章は一転して、あっさりと軽やかな演奏だった。全体の構成を考えていたのかもしれないが、もう少し旋律の美しさに目を向けたほうが良かったのではないかと思う。最後はベートーヴェン《ピアノ・ソナタ第31番》が演奏された。嘆きの歌から復活して歓喜の世界に至るまでの経緯が、よく描きこまれていた。佐藤自身の思い入れもあったのかもしれないが、ドラマがあった。素晴らしい演奏だった。
(5月30日、浜離宮朝日ホール)
(伴玲児)
ムジカノーヴァ 1995年 6月号より
佐藤 季子 ピアノリサイタル
プロコフィエフ特有の肌触りの熱演で全力投球のデビュー
佐藤季子(ひでこ)は東京音大、ワルシャワ音楽院、クラコフ音楽院などに学び、
山口喜久子、志村安英、井口愛子、中島和彦、関根有子、ダン・タイ。ソン、カジミエシュ・ギェルジョド他に師事して昨年末に帰国した若手で、この間ヨーロッパをはじめ諸外国でコンクール、講習などを受け、またオーケストラとの協演も経験している。
今回のリサイタルが(たぶん)日本でのデビューらしいが、そのプログラムはモーツァルトの《ソナタ・K三三二》、ショパンの《ノクターン第十六番》、《舟歌》《アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ》、プロコフィエフの《ソナタ第六番》というもの。もっともこのうち《アンダンテ・スピアナート…》はなんの予告もなく、カットしてしまった。
さてその演奏だが、過度な緊張がありあり。モーツァルトは硬質の明快な響きで音の粒立ちも好いが、そのテンポの速いこと。アレグロがプレストぐらい。第二楽章で安定した瑞々しい歌を聴かせ、両端楽章との対比を際立たせてこの曲の軽快・華麗な曲想を強調したけれど、終楽章のアレグロもまたプレストみたい。もう少しテンポを抑えて欲しかった。
プロコフィエフは全力投球の演奏。狂暴な第一楽章、第三楽章の倦怠感、終楽章の突進力など、プロコフィエフ特有の硬質の冷たい肌触りを感ずる。しかし惜しむらくは音量の割には作品の持つダイナミズムと厳しい緊張感が希薄なことが、作品の強靭な性格を弱めてる。
(4月6日、津田ホール)
佐野公男
佐藤ひでこ紹介文2
佐藤ひでこの演奏を聴いたのはいつのことであったか...プロコフィエフの戦争ソナタを弾いていたのだがそれは凄まじいまでのテンションであった。音に対しての非常に鋭敏な感覚を持っており美しい音はもちろんのこと必要とあらばきつい音を出すことも厭わない。堅苦しいピアニストが多い中なんという爽快感であろうか。その上楽譜に囚われずその裏にあるものを本能的に感じ取って演奏している。作品からここまで色々な要素を読み取り指に伝えることのできるピアニストはそういるものではない。また、瞬間の閃きを大事にする為意外な表情や想像を超えたものが生まれるのだ。その表情それぞれが切れ込んだいわゆる攻めの表現なので聴き古された曲も何が起こるかわからない楽しみがある。構成も素晴らしい、このプロコフィエフもまず客観的に
しかしどっしりと構築されており堅牢な建築然とした様相であった。この類い稀な構成力と野性本能的な躍動、即興性が結び付いた時、演奏としてはもうこれ以上何を望もうということになってしまう。当然の事ながらショパンもまったくもって独創的であった。葬送ソナタの終楽章など信じられない音が浮かび上がり恐ろしい程の集中力のもと美しくもグロテスクな世界観を作り上げていた。演奏を聴くというよりも固唾を飲んで見守る様な体験であった。これこそ真の芸術というべきであろう。
佐藤ひでこの別の顔として完治が難しいとされるピアノジストニアを発症するも自身のリハビリのみで完治させたほぼ前例のないピアニストというものがある。その経験を基に自ら学会で発表する程学究肌の面も併せ持つ。現在治療法もまとめ上げられているという。佐藤ひでこは様々な意味で稀有なピアニストなのである。
森 曠士朗 (音楽評論家)
佐藤ひでこ紹介文
2020年の2月のこと、筆者は、思いがけずして非常に幸福な体験に遭遇することになった。それは、佐藤ひでこ氏の演奏との出会いである。彼女は、東京音大を卒業後、ダン・タイ・ソンの直弟子となって各国で多くレッスンを受けた他、ポーランドのショパン・アカデミーやクラコフ音楽院でも学んだピアニストである。それ以後は、ヨーロッパ各地で研鑽を積みながらかなり華やかな活動を行っていた模様であるが、1995年に帰国した直後にフォーカル・ジストニアを患い、約21年間試行錯誤し続けた結果、彼女独自の鍵盤リハビリのみで2016年に完治したという数奇な運命をたどった人物である。そして、思いがけない運命に苦しめられた彼女は、シャープな感性と純粋無垢で真摯な音楽性の持ち主であり、そのナイーヴな心で各作品に秘められたロマンや作曲家の心情を豊かに感じ取り、それを物おじしないで大胆に前面に押し出すことによって、とても純度が高くセンシティヴな表現を聴かせていた。彼女独特の透明度が高く磨き上げられた音楽は、感情表現の豊かさに於いてもみるべきものがあったが、そうした演奏を聴きながら筆者の心に浮かんできたのは、「あるいは神は、彼女の魂と音楽を一層清め、さらに純粋なものへと磨き上げるために、難病というかたちで厳しい試練を与えたのではないだろうか」といったとりとめのない空想であった。彼女の音楽は、それ自体としては極めて自然でクセのないものであり、透明度の高さや特有の清らかさを随所で強く印象づけていたが、音楽をこうした捉え方ができることは、別の角度から考えると非凡な個性以外の何物でもなくこのピアニストが非常に貴重な才能を有している事実を実感させた。ここまで以前に執筆した批評文を流用しながら彼女の独自性について語ってきたが、今回こうして彼女のデビュー盤がリリースされるのは、筆者としても大変嬉しいことである。ここに聴く彼女の演奏は、以前のリサイタルの時と本質的には違いがないが、さらにその持ち味が磨かれていることが好ましく、そこでは、作曲家の魂と彼女の魂との邂逅が実現されている様相をも随所で感じ取ることができたのである。
柴田龍一
(フォンテックCD FOCD9889ライナーノートから転載)
ぶらあぼ 2020年2月号 (Pick Up) より
佐藤ひでこピアノリサイタル
苦難を超えて突き詰める、美しい音色の世界
佐藤ひでこは東京音楽大学経てポーランドに渡り、同地を拠点にロシア、カナダなど世界を巡って研鑽を積んだピアニスト。名教師であるロシア・ピアニズムの伝道者であるゲンリフ・ネイガウス20世紀を代表するピアニストのエミール・ギレリスの孫弟子としてロシア・ピアニズムを会得し、自らの研究した奏法を結び付けて独自の奏法を編み出している。帰国直後の1995年にはフォーカル・ジストニアに罹患。21年に及ぶ懸命なリハビリを経て、見事に完治。2018年のリサイタルは大盛況となった。美しい音色が高く評価されている佐藤が今回演奏するのは彼女の”核”ともいえるショパンのピアノ・ソナタ第2番をはじめ、シューマンの「蝶々」とブラームスの「三つの間奏曲」いずれの高い技術と歌心、そして研ぎ澄まされた高い音色が求められる常に奏法を研究し音色に対する強いこだわりをもつ彼女だからこそ展開できる音世界をぜひ味わってほしい。
文:長井進之介
ショパン 2020年 4月号より
2月27日 / 東京文化会館小ホール 佐藤ひでこピアノリサイタル
佐藤ひでこ
スコアの彼方から聴こえてくるファンタジー」
奏者は、ロシアンピアニズム教祖ゲンリヒ・ネイガウスの弟子やダン・タイ・ソンに師事し、ワル シャワ他ヨーロッパ各地、カナダで研鑽を積むが、帰国直後フォーカル・ジストニア発症。21年におよぶ闘病の末2016年に完治、演奏活動再開。冒頭のブラームス《3つのインテルメッツォ》第1曲を耳にした瞬間、その優しさと暖かさに満ちた響きに引き込まれる。遠い過去に万感な思いを馳せ、全てを許し、また受け入れるかのよう……。第2曲も、旋律とバスとの調和が美しく、音楽の真実にあふれる。第3曲は、波立つ心に、かすかな希望と祈りが訪れるよう……。次に、シューマン《パピヨン》。何と自由に美しく飛翔する音楽だろう!ポエジーと香り立つロマンティシズムが聴くものにファンタジーを贈り届ける。後半はショパンのピアノ・ソナタ第2番《葬送》。デモーニッシュなスタートからすでにただならぬ表現力を感じる。決してアグレッシブにならず、絶えず優しさと気品が漂う一方、劇的な表現力を有し、音楽そのもののスケールが大きい。2楽章も緊迫感から一転ノスタルジックな中間部が美しい。3楽章の葬送行進曲は悲しみを深く個人的にとらえ、荘重な中、突き抜けるような透明な音楽が流れる。中間部の歌も限りなくピュアで優しい。フィナーレは幽玄で厳粛。最後の一音を敢えてPPで表したところに奏者の深い意図を感じた。
(藤巻暢子)
音楽現代 2020年5月号より
演奏会評 ピアノ・鍵盤楽器から
佐藤ひでこ ピアノ・リサイタル
この日も振袖で履物なし。上体が固定されて無駄な動きなく、案外弾きやすいのでは。ただ聴き手にとって着物姿は重要でない。ブラームス / 3つの間奏曲作品117は自分を消していくように黙考から入っていった。寂寥感で覆われる。ドイツ・ロマンが幽玄と結びついた淑やかな歌い。ゆったりとした腕の上下動が手首を軸に指の圧を微調整する、ロシア奏法。しかも求める音がそうさせている。シューマン
/ パピヨンも詩を朗読するような抑揚がつく。どのモチーフも閃きに溢れ、着想がはじける。ショパン / ソナタ2番の大きな跳躍に難はなかった。1楽章、独特のシンコペーションを刻みながら長大なフレージング、やはりロシア流。〈葬送〉の悲しみはありえないほどの心底に沈み、プレスと楽章はまさに再創造。時間が圧縮され、リレーフのような造形を浮かび上がらせる。身を投じるあまりもったいない場面もあったが、場数の問題だ。比類ないピアニストでありアーティストを今後もフォローしていく。
(2月27日、東京文化会館小ホール)
(高塚昌彦)
ムジカノーヴァ 2020年 5月号より
演奏会批評 関東の演奏会から
佐藤ひでこ
佐藤ひでこは、東京音大を卒業後、ダン・タイ・ソンの弟子となって各国でレッスンを受けた他、ポーランドのショパン音楽院やクラコフ音楽院も修了したピアニストである。それ以後の彼女は、ヨーロッパ各地で研鑽を積みながら演奏活動を行っていた模様であるが、1995に帰国した直後にフォーカル・ジストニアを患い、約21年間試行錯誤し続けた結果、独自の鍵盤リハビリのみで2016年に完治したという数奇な運命をたどった人物である。そして 、当夜の彼女のリサイタルでは、ブラームスの《3つの間奏曲》、シューマンの《パピヨン》、ショパンの《ピアノ・ソナタ第2番「葬送」》が演奏された。佐藤は思いがけない運命に苦しめられた一方、非常にシャープな感性と純粋で真摯な音楽性の持ち主であり、そのナイーブな心でそれぞれの作品に秘められたロマンを豊かに感じ取り、それを物おじしないで大胆に前面に押し出すことによって、とても純度が高くセンシティブな表現を聴かせていた。彼女独特の透明度が高く磨き上げられた音楽は、感情表現の豊かさにおいてもみるべきものがあったが、そうした演奏を聴きながら筆者が感じたことは、「あるいは神は彼女の魂と音楽をさらに純粋なものに磨き上げるために、病気というかたちで厳しい試練を与えたのではないだろうか」といったとりとめのない空想であった。彼女の音楽は、それ自体としては極めて自然でクセのないものであり、透明度の高さや特有の清らかさを随所で強く印象づけていたが、音楽をこうした捉え方ができることは、別の角度から考えると非凡な個性以外の何物でもなく、このピアニストが非常に貴重な才能を有してる事実を実感させた。今後の活躍が楽しみであり、\大輪の花を咲かせてくれることを祈りたい
(2月27日、東京文化会館小ホール)
柴田龍一
ぶらあぼ 2018年5月号 (5月の注目公演) より
佐藤ひでこ(ピアノ)
5/30(水)19:00浜離宮朝日ホール
東京音大からポーランドやカナダに学び、国際派ピアニストとして将来を嘱望されていた矢先、難病に侵され 、やむなく活動を停止した佐藤ひでこしかし、2年前に奇跡的に回復を果たし、今年3月には「23年ぶり」のリサイタルを成功させた。今回はベートーヴェンの31番、シューベルト第13番、プロコフィエフの第6
番と3つの名ソナタを軸に。蘇ったロシアン・ピアニズムで紡ぐ美音に、奏でる喜びを託す。
(文・笹田和人)
ショパン 2018年 8月号より
佐藤ひでこピアノリサイタル 5月30日 / 浜離宮朝日ホール
23年ぶりのリサイタル、生命力に満ちた情緒豊かな表現
欧州やロシアなどで学び、研鑽を積んだ佐藤ひでこは帰国後のデビュー公演後にフォーカル・ジストニアに罹り、思うように動かせなくなって20年以上も弾くことができなかった。それが一昨年に完治を遂げた。この復活リサイタルではドビュッシーと三曲のソナタを選曲、まったくブランクを感じさせない優れたテクニ
ックを駆使して、作曲家と作品への深い理解を思わせる真摯で様式感のある表現で聞かせた。ドビュッシーの二曲〈パックの踊り〉での軽やかさ、気まぐれの味も出しつつ、なめらかに飛びまわり、リズミカルに踊るよう、〈ミンストレル〉では神経質な空気を作りつつ、機知に富む表現で奏された。三曲のソナタ、プロコフィエフの《ソナタ第6番》をエネルギッシュに、独特の叙情性も充分表し、とりわけ第1楽章はダイナミックに、やがて深みへと入り込み、終楽章では高音の際立つ疾走、第1副主題も印象的に、勢いのある弾奏で聞かせた。一方シューベルトの《ソナタ第13番》D664では自然な表現で、旋律の素朴な味を引き出し、ときに心を透くような清澄さ、とりわけ第3楽章は流麗で、リズムの魅力も感じられた。最後はベートーヴェンの《ソナタ第311番》作品110、第1楽章でのしみじみとした味わい、情緒豊かに移りゆき、第2楽章は程良く強弱がつけられ、中間部が足早かつ軽やかに表された。終楽章は内なる声のよう、切々と紡がれ、フーガでは遭進するような奏楽、その頂点は確信的で生命力に満ちあふれる弾奏となった。
(菅野泰彦)
音楽現代 2018年 8月号より
佐藤ひでこ ピアノ・リサイタル
手の病のため演奏を休止、克服して開いたリサイタルは23年ぶりのとのこと。だがブランクは感じさせない。なんと着物で登場。そのユニークさは演奏にも表れる。ドビュッシー/パックの踊り、ミンストレル。音楽は凸凹豊か、抜群のリズム感で弾ませる。なのに潤いある音質。入り出のフレージングの妙、間どりも巧み。これらと繋がりよくプロコフィエフ/ソナタ6番。「戦争ソナタ
」と床の付く振袖、締め付ける帯は不思議な光景。体の動きは制約され、キュービック気味になるけど、なぜかプロコフィエフに適合。打鍵はキッチリガッチリ、でも脱力して・・・その瞬間、どこかの>に全体重をのせ、完全に立ち上がった。でも決して乱暴ではなく、求める音に完全に奉仕。後半にシューベルト/D664、ベートーヴェン/ソナタ31番。技術を切り替え、和風の淑やかさへ移行させたが、やはりプロコのffが残って集中を削がれたよう。1日で2つの離れた高峰は避けるべき。とはいえ、見る価値もあるリサイタルは初めてだ。
(5月30日、浜離宮朝日ホール)
(高塚昌彦)
ムジカノーヴァ 2018年 9月号より
演奏会批評 関東の演奏会から
佐藤ひでこ
長く患っていたフォーカル・ジストニアが完治しての復帰リサイタルだという。しかし当夜の演奏にはジストニアの影響は微塵も感じられなかった。人知れぬ苦労があったとは思うが、見事である。佐藤は良い意味で楽曲によってスタイルが変わるピアニスト。前半と後半では別の魅力があった。前半のプロコフィエフ《ピアノ・ソナタ第6番》では、敢えて作品と自己の距離を取り、差し迫った焦燥感を前面に出すのではなく、精緻な楽曲の構造をよく理解して、第4楽章で集中度が最大になるように全体を統一的にまとめあげていたメカニックが安定していたからこそ、第4楽章が躍動感に満ちた演奏になったのだろう。後半では、まずシューベルト《ピアノ・ソナタ第13番》D664が演奏された。イ長調のソナタの魅力を、佐藤は心からの歌で優しく表現していた。第2楽章のパストラルは印象に残った。素晴らしかった。第3楽章は一転して、あっさりと軽やかな演奏だった。全体の構成を考えていたのかもしれないが、もう少し旋律の美しさに目を向けたほうが良かったのではないかと思う。最後はベートーヴェン《ピアノ・ソナタ第31番》が演奏された。嘆きの歌から復活して歓喜の世界に至るまでの経緯が、よく描きこまれていた。佐藤自身の思い入れもあったのかもしれないが、ドラマがあった。素晴らしい演奏だった。
(5月30日、浜離宮朝日ホール)
(伴玲児)
ムジカノーヴァ 1995年 6月号より
佐藤 季子 ピアノリサイタル
プロコフィエフ特有の肌触りの熱演で全力投球のデビュー
佐藤季子(ひでこ)は東京音大、ワルシャワ音楽院、クラコフ音楽院などに学び、山口喜久子、志村安英、井口愛子、中島和彦、関根有子、ダン・タイ。ソン、カジミエシュ・ギェルジョド他に師事して昨年末に帰国した若手で、この間ヨーロッパをはじめ諸外国でコンクール、講習などを受け、またオーケストラとの協演も経験している。 今回のリサイタルが(たぶん)日本でのデビューらしいが、そのプログラムはモーツァルトの《ソナタ・K三三二》、ショパンの《ノクターン第十六番》、《舟歌》《アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ》、プロコフィエフの《ソナタ第六番》というもの。もっともこのうち《アンダンテ・スピアナート…》はなんの予告もなく、カットしてしまった。 さてその演奏だが、過度な緊張がありあり。モーツァルトは硬質の明快な響きで音の粒立ちも好いが、そのテンポの速いこと。アレグロがプレストぐらい。第二楽章で安定した瑞々しい歌を聴かせ、両端楽章との対比を際立たせてこの曲の軽快・華麗な曲想を強調したけれど、終楽章のアレグロもまたプレストみたい。もう少しテンポを抑えて欲しかった。 プロコフィエフは全力投球の演奏。狂暴な第一楽章、第三楽章の倦怠感、終楽章の突進力など、プロコフィエフ特有の硬質の冷たい肌触りを感ずる。しかし惜しむらくは音量の割には作品の持つダイナミズムと厳しい緊張感が希薄なことが、作品の強靭な性格を弱めてる。
(4月6日、津田ホール)
佐野公男
佐藤ひでこ紹介文2
佐藤ひでこの演奏を聴いたのはいつのことであったか...プロコフィエフの戦争ソナタを弾いていたのだがそれは凄まじいまでのテンションであった。音に対しての非常に鋭敏な感覚を持っており美しい音はもちろんのこと必要とあらばきつい音を出すことも厭わない。堅苦しいピアニストが多い中なんという爽快感であろうか。その上楽譜に囚われずその裏にあるものを本能的に感じ取って演奏している。作品からここまで色々な要素を読み取り指に伝えることのできるピアニストはそういるものではない。また、瞬間の閃きを大事にする為意外な表情や想像を超えたものが生まれるのだ。その表情それぞれが切れ込んだいわゆる攻めの表現なので聴き古された曲も何が起こるかわからない楽しみがある。構成も素晴らしい、このプロコフィエフもまず客観的に
しかしどっしりと構築されており堅牢な建築然とした様相であった。この類い稀な構成力と野性本能的な躍動、即興性が結び付いた時、演奏としてはもうこれ以上何を望もうということになってしまう。当然の事ながらショパンもまったくもって独創的であった。葬送ソナタの終楽章など信じられない音が浮かび上がり恐ろしい程の集中力のもと美しくもグロテスクな世界観を作り上げていた。演奏を聴くというよりも固唾を飲んで見守る様な体験であった。これこそ真の芸術というべきであろう。
佐藤ひでこの別の顔として完治が難しいとされるピアノジストニアを発症するも自身のリハビリのみで完治させたほぼ前例のないピアニストというものがある。その経験を基に自ら学会で発表する程学究肌の面も併せ持つ。現在治療法もまとめ上げられているという。佐藤ひでこは様々な意味で稀有なピアニストなのである。
森 曠士朗 (音楽評論家)